
Copyright(C) 2002.hai
ここだけのはなし2002 バックナンバー 睦月 / 如月 / 弥生 / 卯月 / 皐月 / 水無月 / 文月 / 葉月 / 長月 掲載された記事を許可なく転載することを禁じます

Copyright(C) 2002.hai
ここだけのはなし2002 バックナンバー 睦月
/ 如月 / 弥生
/ 卯月 / 皐月
/ 水無月 / 文月
/ 葉月 / 長月 掲載された記事を許可なく転載することを禁じます
|
|
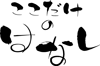 |
遅刻の誕生。 雪景色が見たい。 大人の万年筆。 先日、知人からフランスのお土産として万年筆を頂戴した。仕事柄、文字を書くこと
を気遣ってくれたのだろう。早速、手にしてみるとなんと軽いことか。その濃茶色の
半透明ボディ「ウォーターマン」に、懐かしい感じがするインクカートリッジを差し込み、試し書きをしてみた。とても書きやすいのですっかり気に入ってしまった。 ひらがなが、お好き!? 昨日、仲間たちとの会話のなかで、携帯メールの話で盛り上がった。それは、今の子供たちの間では文字より記号を用いてコミュニケーションをとっているという。大人が見ても本人に聞かなければわからないメール文だという。日本語は進化するのはいつの時代も同じだが、記号化されていくことに抵抗を感じるのは大人のほとんどだろう。象形文字から漢字が生まれたことくらいは誰でも知っているはずなのに、今度は言葉を略して記号化する。しかも、デザイン的に限定された記号の中から選んでの話だ。仕事柄、絵文字や絵言葉ともいえるピクトグラムを作ることはある。非常階段とか、トイレなどのマーク、つまり絵だけで伝達する記号。その考えからいえば、意味不明の記号が多いのではないだろうか。もっとわかりやすい、グッドデザインを入れて欲しいものである。 社会へのプレゼンテーション。 いま芸術系の学校では、卒業制作の季節である。ある学校の非常勤講師として受け持つ学生たちも、急ピッチ(?)で仕上げにかかっている。昨夜も午前4時すぎまでかかって企画書を仕上げたらしい。というのは、本日が研究課題として取り組んできたテーマ「京のまちクリーンアップ作戦」のプレゼンテーションの日なのだ。この日のために、学生たちは休日ともなれば観光地に出かけ、アンケートや街頭インタビューで生の声を収集したり、ポイ捨てされている現場を写 真に納め、それらを分析し、美化につながるヒントをひねりだしてきた。コンセプトの発見に至るまで長い時間を要したが、それぞれにポスターに仕上げ、それを説明するための趣意書ともいえる企画書を完成させた。プレゼンの相手は行政である。午後2時、担当の課長を含め4名の方々が、貴重な時間を学生たちのためにさいてくださった。一人が全体の考えを述べ、個々の作品に関しては制作者が説明をおこなった。まぁまぁ上手にできたのではないかと思う。相手の質問に関しては、意見が統一できていなかった点が少し惜しまれるが、ま、今後の役に立つのではと思った。もちろん、偉そうにいう私もプレゼン慣れしている訳ではない。何事も経験を積み重ね、失敗して少しずつ社会を知っていくのだろう。残念ながら一生懸命やった研究課題だが、相手の反応はいまひとつだった。個人的には相手が喜ぶものと信じていただけにショックは隠しきれなかった。社会の厳しさを学生たちと体験したプレゼンだった。こちらも、はやく大人になろうっと。(2002.01.24) 「おとな」という日本語は「おとなしい」の元のことばだ。
時代はつり上がった眼?! 最近のクルマは、なぜあんな顔をしているのだろう。デザインが気になる。特に、ヘッドラランプの形だ。つり上がった眼である。奈良美智さんのアニメキャラクターも、少女の太めの三日月のようにつり上がった眼。その共通
点が気になっていた。たぶん私だけではないと思う。そんなある日、哲学者の鷲田清一さんが日経新聞「あすの話題」でこの点に着眼されたエッセーがあるので引用させていただく。 ほんの少しずつ春へ。 寒さ厳しい早春の朝。まだ冷たい空気のなかで、膨らんだ蕾がほとんどだったが、ほんの少しだけ一輪一輪と梅の花を咲かせていた。梅の甘く優しい、芳しい香りは花以上に愛でられ、日本人に最も愛されてきた。梅は春告花として、また松竹梅と嘉祥木のひとつとして、古くから日本人が開花を待ちこがれる花であった。万葉集では萩についで多く詠まれ、かつて花といえば梅の花のことをさした。そもそもの原産地は中国であり、日本へ薬用として渡来したのはかなり古い。梅は花とともに、実も楽しめる貴重な木。長い時を経て、果 実を食材として利用することも含め、梅の品種改良と栽培が日本各地でおこなわれてきた。梅といえば、菅原道真公を連想するほど有名な北野天満宮。五十種二千本以上のスケールと背景の社殿の美しさで、名実ともに日本一の梅の名所である。今朝、北野天満宮へお詣りに行ってきた感想である。(2002.01.19) グラフィックデザイナー 田中一光さん デザインの世界に「着地」という比喩がある。「デザインの目的」という到着地に着陸できることをいう。どうしてこんな航空用語が使われたのかは不明であるが、私にとっての語源は亀倉雄策氏の「離陸着陸」というデザイナーにとってバイブルのようなエッセイ集があって、その小編に由来している。
むかしデザイナーの先輩たちから「田中一光のデザインはビスが一本足りないなあ」とよくいわれた。何のことかよくわからなかったが、つまり機能的な説得力に欠けることをいうのだそうだ。ファインアートとの基本的な違いは、この「発想の着地点」があるかないかなのである。それを私なりに理解してビスや着地で頭がいっぱいになった時期がある。 夢中になること。 私にとってのスポーツといえば、自慢できるものなど何ひとつない。でも、その時々に夢中になっていたことを思い出す。中学時代にやっていたバスケットボール。社会人になりたての頃、覚えたテニスとスキー。そして30代の手前で免許を手にしたバイク。当時は、河原や山でのモトクロごっこで泥んこになって遊んでいた。仲間とのツーリングもよく行った。そうそうマラソンにも2年連続で参加した。といっても、たった10kmだが、結果 はきりきりの制限時間内。40代後半でダイビングの魅力にはまり奄美大島通い。だが、息遣いがあらいせいか潜水時間は人よりも短い。そしてカメラをぶらさげて山歩き。とにかくスポーツは楽しむもの。少しくらいは上手になろうと思ってはいるものの、なかなか運動神経と体力が意に反してしまう。人に迷惑をかけない。自分なりに努力はするが、そのまま技術の向上に繋がったり、他の人との優劣が目に見えるというものではない。それだけに、スポーツは自分にとって意味があればそれでよいわけだ。無理せず、自己を解放してやると、なんと気持ちのよいことか。息を切らして汗を流せば、心地良さが倍増するみたいだ。(2002.01.16) 神様、怒ってない!? この正月にお世話になった〆縄や正月飾りを感謝と祈願をこめて燃やす「とんど」
(地方によっては「どんと焼き」とか呼び方はいろいろ)。とんどに、書初めを燃やすと、字がうまくなると小さい頃、祖母から聞かされたことを思い出しながら、昨日、近くの吉祥天満宮にとんどに出掛けた。初詣以来の参拝だ。境内では大きな火が
勢いよく炎と煙が上がっていた。それを囲むように大勢の参拝者が次々と正月飾りを
ほりこんでいく。焼けた藁の灰が空から降ってくる。ミカンの焼けた匂いもする。私の故郷では、自分とこの分の灰を持って帰り、家のまわりにまき、厄除けとしていた。
たぶん今も続いていると思う。こういった風習って若い時には良さがわからないものだが、時代や世代が変わってもいつまでも絶えてほしくないものだ。境内では、毎年この時期に子供たちの書初め展が開かれ、こちら目当てにも多くの人たちが訪れている。 大人になれない「成人式」。 数年前から、ハッピーマンデー法とかで1月の第2月曜日が「成人の日」で世間はお休み。こちらも連休で、朝からのんびり。だが、どうも1月15日で長い間育ったものには未だしっくりこない「成人の日」だ。昔は、元服といって男子の成人を意味し、元服式で初めて冠りものを被り、幼名を改め、大人の服を着たといわれる。時代は変わっても、街は成人を迎える若者たちの晴れ着姿があざやかに映る。華やいで気持ちいい世界だ。朝早くから美容院と着付け、記念写
真と忙しかったのだろうなと余計なことを考えてしまう。最近は男性の着物姿もちらほら。なかには、芸能人も顔負けのカラフルな羽織袴姿もいる。茶髪にピアス、ひげ、ケータイなど、ファッションと共に時代はどんどん変わっていく。おしゃれは自
由に楽しめばいい。ただひとつ、絶対にやって欲しくないのは二十歳になった大人としての自覚だ。どうかすてきな大人になっていただきたい。まずは、成人おめでとう。 音で熟成する想像力。 「遠い地平線が消えて ふかぶかとした夜の闇に心を休める時 はるか雲海の上を音もなく流れ去る気流は たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果 てしない光の海を 豊かに流れゆく風に心を開けば きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜の静寂(しじま)のなんとと饒舌なことでしょう。光と影の境に消えていったはるかな地平線も瞼に浮かんでまいります。夜間飛行のジェット機の翼が点滅するランプは 遠ざかるにつれ次第に星のまたたきと区別 がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように…」。懐かしいと思われる方は、同世代か人生の先輩。学生の頃からよく聴いていたFM大阪(発信はFM東京)の「ジェットストリーム」。いまは亡き城達也さんのナレーションではじまる深夜0時からのラジオ番組である。かかる音楽は選曲抜群でイージーリスニングとなり、まだ行ったことのない異国の地に思いを馳せていた。毎晩のように、夢先案内人である城達也さんの声と音楽によって、心地よい夢を見ていた頃が懐かしい。音文字だけのラジオによって、想像する楽しみを知らず知らずの間に覚えていたのかもしれない。あのナレーションを書いていた放送作家ってどんなひとなのだろう。いまから思うと、上手に構成されていたなと感心するばかりだ。(2002.01.12) 初えびすで商売繁盛!? 十日えびすに行くようになったのは、いつ頃からだろうか。毎年、正月が明けると一年間お世話になった吉兆笹を持って、恒例のように出掛ける。四条通 から大和大路通を南へ歩き始めると、両サイドは屋台がずらりと立ち並び、祭気分は自然と高まってくる。この雰囲気が好きなのかな。露店で狭くなった道を沢山の参拝客が埋め尽くす。途中で、酒屋さんの前で升酒をぐいっと呑みほし、身体をあたため、体内を浄める。恵比須神社に近づくと人の流れはほとんどスローモーション。なんとか境内に辿り着くことができても人の山。吉兆笹を授かるまで長い列ができている。ようやく手にして、こんどは鯛、福俵、宝船、千両箱、絵馬などの縁起物をぶら下げてもらうのがこれまた楽しい。ちょっと高くつくがを神様だ、仕方がない。由来は、恵比須神が正月10日の寅の刻に生まれたといわれ、十日えびすは恵比須さんの縁日にあたるらしい。商売繁盛と家内安全の神様、がんばりまっせ。今年もどうかよしく。(2001.01.11) 家庭用フランス料理。 昨夜、ある店で食事を楽しんだ。以前から気にはなっていたのが、恥ずかしい話なかなか入る勇気がなかった。職場の3人で訪れた店内は、なかなかあたたかな雰囲気のいい感じ。カップルをはじめ、若い女性たちで賑わっていた。顔見知りのお店の人に聞いてメニューを決め、ついでにワインも注文。料理が出てくるまでに出されたのが、名前は忘れてしまったがハーブなどに漬込んだ色濃いオリーブの実が6つ(ノルマは1人2個)。つまようじにささって登場したので、さっそく口に。思わずウー、なんだこれは?と思ったのはみんな同じだった。この味というものは、まさに言葉にすることができない。ただ、まずいだけではすまされない。口のなかにオキシドール(消毒液)を含んだ感じだ。他の比喩が思い浮かばないほど、口でカルチャーショックを覚えた。フランス人は本当にこんなのを食べているのだろうか。一瞬どころか、いまでもそう思っている(お店の人ごめんなさい)。そのおかげかどうかはしらないが、後に出てきた料理の美味しいこと。最後のデザートまですっかり戴いた。昨夜の香辛料の強いおかげで、本日は口臭どころか、食欲がわかないのは歳のせいかな?刺激が強すぎたみたいだ。単に身体が冷えきっており、疲れていたからだろうか。ところで、味覚を表現するのは難しい。美味しい、うまいだけでは白ける。そこで、さまざまな比喩を用いて表現しようとするが、これまた厄介である。ところが、文章表現の上手な人の手にかかると、味も、匂いも、さらには温かみまで、その通 りに伝わってくるから不思議である。もっともっと勉強しなきゃ。(2001.01.10) 予知できないモノの生命。 ある日突然、ノートパソコンが壊れた。その翌日、クルマが動かなくなった。どちらも大事に使っていた必需品だけに、困るというより不便で仕方がなかった。機能を果 たさなくなる前に、何かの兆しや予感があるのではといわれそうだが、今回は何ひとつ感じられなかった。モバイル用のノートパソコンは、開いたら画面 側のバネ?がきかなくなり、180度倒れてしまった。使う時は画面の後側に、食卓にあったリンゴを置いて角度を調整するという原始的な方法しかなかった。年明け早々、保証書持参で販売店へ持ち込んだ。まだ7ヵ月目に突入というのに、店員の応対でさらに腹が立った。というのは、1年間保証というのに「修理見積りをとるだけで費用がかかるので、いくらまでなら修理可能か」と聞いてくるではないか。しかも修理に1ヵ月はかかるという。なおしてもらわないと使えない。頼れるのは販売店しかないというのに。マニュアル通 りの応対にハートが無さ過ぎる。なんか弱みに付け込んだ商法みたいで気分悪かった。愛車の方は、ドライブ中にバッテリーが上がってしまったのだ。目的地の途中で、休憩しようと停車したらそのまま動かなくなった。クルマ大好き人間としてはショックだった。なんかドライバー失格のような気がした。もちろん、バッテリーが冬の寒さに弱いことくらい知っている。昨年の春、車検時に交換してもらったバッテリーですぞ。こちらも7ヵ月目。毎日乗っているが走行もしれている。あら悲しい、保証期間は6ヵ月。また修理代が怖い。そりゃ、モノにはアタリ、ハズレがあるだろうが、同時にふたつはキツイぜ。(2001.01.09) 愛宕山詣り。 のんびりと過ごした正月で身体も休養し過ぎたみたいだ。というのは、今年も上田真三さんの会社(株式会社枡儀)の新年会に参加してつくづく感じたからだ。新年会といっても、単に御馳走とお屠蘇で祝うのではなく、みんなで愛宕山にお詣りに行き、帰りは水尾(柚の里)へ降りて、柚風呂に入り、それからが宴会という充実した一日が送れる内容となっている。朝八時十七分、JR花園駅に集合し、清滝から歩き出したものの、仲間から外れていくばかり。前半はマイペースでいいかと思って息遣い荒く一歩一歩前へと登り始めた。しかし、体調と気分は最高にいいのに、なぜか足が重い。静かな山へ一歩を踏み出し、順調に歩き出したはずなのに、半時間ほどで、足は鈍り、息も切れてしまった。どうすれば、もっと楽に山歩きが楽しめるのか、以前に上田さんに聞いたことを思い出した「最初から飛ばし過ぎ。自分でも遅いなと思うスピードで歩くこと。とにかくゆっくり、ゆっくり。それが準備運動となって、次第に歩く速さがつかめてくるよ。そして気がつけば、山登りってなんて楽なのだろうと思う。そうなれば一人前だよ(笑)」。ところが、その自分でも遅いと思う速さで歩くことの難しいこと。普段何気なく歩いている人間にとっては、少しでも早足こそが健康づくりにつながると思っていただけに、その言葉には重みを感じた。ゆっくりと歩くことは実に難しい。最初の一歩とはうまくいったものだ。無理せずマイペースで、山登りを楽しむ。何度も休憩してもよし、ただひたすらに頂上をめざし、歩き続ける。滝のように流れ落ちる汗を拭いながら、ゆっくりと駆け上っていく。山の上から望む光景の素晴らしさは、きっと汗の恩恵なのだろう。だが、恥ずかしい話、今回は特に山の長い階段はとてもしんどかった。途中の平坦な道で時間を縮めればいいかと思ってはいたが、先頭から遅れること半時間。頂上付近ではちらちらと雪も降り、足元はアイスバーン状態。こけるまいと神経をつかいながらようやく参拝ができた。ここは昔から、火の神さんで名高い。京都人ならよくご存知の「火迺要慎」と書かれた愛宕(阿多古)神社の御札を授かって水尾へ下山。新年早々から、身も心も清らかになれた一日だった。いい機会を与えてもらえたことに感謝。本日の教訓「もう少し身体を鍛えておこう」(2002.01.05) うれしい年賀状。 毎年、新春に届く年賀状を手にして思うのは、これだけ多くの人との出逢いがあったことに驚かされる。一人ひとりの出逢いに、心から感謝。ことしも知りあった人たちとどれだけ交流が深められるか、そしてどんな人たちとの出逢いが待っているのだろうか。やはりEメールや電話などの年賀の挨拶もあるが、それぞれに凝った年賀状を一枚一枚、読んでいくと顔が浮かび、実にうれしい限りである。景気の低迷を受けて、まっすぐ前へとか、元気に精一杯頑張ろうというメッセージや、初春らしく夢や抱負を題材にした内容が多かった。個人的なものでは、家族の近況報告なんかも和ませてくれる。さぁ、今年も、いや本年こそは勝負の年だ。どうかお付き合いのほど、よろしく。(2002.01.04) ジルヴェスター・コンサート 毎年、大晦日の夜といえば、我が家でNHKテレビ「紅白歌合戦」をみながら年越しそばを食べ、「ゆく年くる年」の頃になると近くの神社へ初詣に出かけていた。しかし、 二年前から新しい年を美しいクラシック音楽を聴きながら迎えるジルヴェスター・コ ンサートに出かけるようになった。昨年の暮れも、びわ湖ホールでカウントダウンができた。『ジルヴェスター』とはドイツ語で大晦日の意味らしいが、こういう素敵な イベントを教えてくれたのは、ハープ奏者の内田奈織さんだ。彼女は毎年のようにこのコンサートに出演しており、お誘いをいただいたのが始まりである。昨年は若杉弘さんの指揮で楽しませてもらったが、今回は松尾葉子さんの指揮でドリーブのバレエ音楽「シルヴィア」より『バッカスの行進』から始まった。ことしは、クラリネット奏者の赤坂達三さんをゲストに迎え、オーケストラとクラリネットの饗宴、オペラの名場面 の曲など、心地よい音楽に浸りながら年越しの瞬間を迎えた。特に、後半のヴェル ディやレハールのオペラ曲が個人的にお気に入り。すべてよかったね。華やかで洗 練された演奏を聴かせてくれる大阪シンフォ二カー交響楽団、高らかな合唱が響き渡 るびわ湖ホール声楽アンサンブル、そしてファンファーレ隊。多くの出演者と観客が ひとつになった夜だった。いい年越しをありがとう。(2002.01.03) 縁起のいい正月。 正はあらためる、あらたまるという意味から、年のあらたまる月が「正月」。昔は「むつき」と呼ばれていた。もっとも古い文献では『日本書紀』をはじめ、『万葉集』にも「むつき」の文字があり、正月になると家がなごやかにむつまじく、楽しい日を送るということからいわれたらしい。今では「睦月」(むつき)の字があてはめられている。他にも、一月の別 称には、初春(はつはる)、初空月(はつぞらづき)、年端月(としはづき)、太郎月(たろうづき)、首歳(しゅさい)、献歳(けんさい)、発歳(はつさい)、霞初月(かすみはつづき)などいろいろ。いずれにせよ、正月は松竹梅と縁起のいい年明け。心新たに、春は「勝ち来る」(かち栗)なんてね。ことしも、よろしく。 (2002.01.02) あざやか水引文化。 鶴・亀・松・竹・梅・宝船・七福神など、めでたい縁起にあふれた正月飾り。鶴は千年の齢と貞節の象徴、亀は万年の齢と夫婦の和合、松は常緑であることから、不老長寿、信義、格調の高いの意があり、竹はたくましい成長力や節の空洞から心身の潔白、正直を示し、梅は酷寒に耐えてみごとな花を咲かせるところから忍耐、努力、剛健を象徴するらしい。人々の繁栄や幸福にまつわる意味をもつものばかりで実にめでたい。特に、純白の和紙に紅白の水引。キリリと結んだ日本ならではの「贈り」の意匠は、実にいさぎよく美しい。用と美を兼ね備え、さらに日本人の心を伝え続けてきた「水引」には、とてつもなく長い歴史がある。水引の発祥は、はるか飛鳥時代、遣隋使小野小町が大陸から持ち帰った朝貢品に遡るらしい。海路の平穏無事を祈って、紅白の麻で結ばれていたそうだ。以来、宮中への献上品はすべて紅白の麻で結ぶ慣例となり、水引文化が始まったとされる。平安時代には、宮中の女性が髪を束ねるのに用いたこよりとして使われ、その後の武家社会においては礼儀作法の確立とともに盛んに儀礼的なものとして用いられるようになり、江戸時代には現代のようなカタチで使われるようになったとされる。水引がまぶしく輝く新たな年の門出。ことしも、よろしく。(2002.01.01) 勇気づけるコピー! 先日、朝刊の声の欄を読んで感動した。それは、かつての広告コピー「めしが、食えて。眠れる場所があって。数少なくても、信じられる友がいて。電車賃も、文庫本も、ある。あと欲しいものは、せいぜいひとつか、ふたつ。財産は、俺だ。俺が、財産だ。立派な正月が、来た。」というものがあったらしい。その投稿者はこのコピーに勇気づけられたという話。それを読んで、コピーライターの自分も凄いと感じてしまった。なんの広告なのか、どこの企業(店)なのか、気になって仕方がないのは僕だけではないだろう。コピーもうまいが、投稿者の文章を借りれば「与えられた現状の中から、できるだけ多くのプラス面 を引き出せば、心の荷物も軽くなるとと教えられた。不況、倒産、失業。何が起こるか分からない世相。大丈夫。朝の来ない夜はない。希望と勇気を失わず、明るい心で新年を迎えたい」。いまの時代にぴったりとあてはまる名文に拍手を贈りたい。(2001.12.29) お菓子が狙う、おいしい職場? |
|